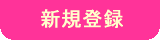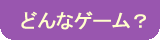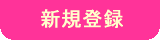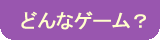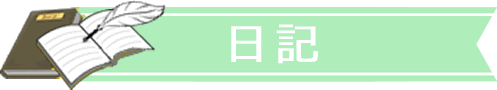母親は悲鳴を止めたがまた直ぐに悲鳴をあげた。
僕は母親を刺した。
悲鳴。悲鳴。悲鳴。悲鳴。
刺すたびにあがる悲鳴は残酷なように思えたが僕は何とも思わなかった。
何故もっと早くやらなかったのか。
こんなにも悲鳴が美しいものだったなんて。
そのうち母は声をあげなくなった。
あぁ…足りない、足りない、足りない、足りない!!!!
頭をかきむしり静かになった母親を見る、ふと思い出す。
妹は?
直ぐに近くにより確かめる、息はある、まだ間に合うとできることはして、妹をベットに置いた。
妹は助かったが、母親は死んだ。
しかしこの快感、今まで溜めたものをだした結果なのだろうか?
もう今はこの快楽に浸っていたかった。
悲鳴と言う快楽に溺れ時間がたつと妹は目覚めた。