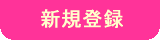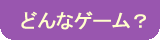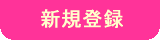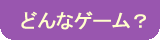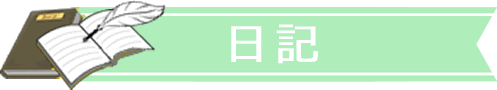僕がよく遊んでいた大好きな飛行機のおもちゃも、父が買ってくれた大切なものだ。でも、そんな父が、ある日言った。
「じゃあ行ってきます。」
僕はただ、
「行ってらっしゃい。」
と、泣きながら言うしかなかった。なぜなら、もう戻ってこないかも知れないのに、、、
その後も、いつものようにお腹がすいても、余った米を食べながら、ただ目の前のラジオで見守ってあげることくらいしかできなかった。僕の友達も、みんな違う学校に通った。下校の時は、外をみても夜なのに、まだ朝かのように明るくて、真っ赤だった。僕の持っているおもちゃが、空に100機ぐらい宙に浮いていた。
それからおよそ6年後のこと、
「トントン」とドアを叩く音が聞こえた。母が急いで玄関を開けた。ラジオのえらい人の声と同時に、もう忘れてしまっていた誰かの骨かなんかが送られてた。