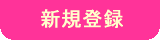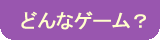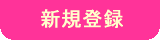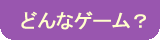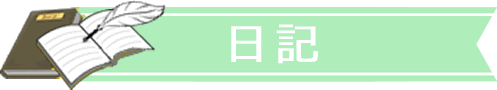重苦しい雰囲気の中で宿の主人は話し終え、そそくさと後片づけのために席を立った。役人はその場での解釈は避け、役所に戻って調査台帳をまとめ終えた頃、懇意にしていた職場の先輩に意見を求めた。先輩は天保年間の村民台帳を調べながら、自らの考えを述べた。
「大飢饉の時には、餓死した者を家族が食したという話を聞いたことがある。しかし、その大木のあった村では遺骸だけではなく、弱った者から食らったのだろう。そして、生き人を食らう罪悪感を少しでも減らすため、牛追いの祭りと称し、牛の頭皮を被せた者を狩ったのではないだろうか。お前の見た人骨の数を考えると、その村に住んでいた村人の数にほぼ相当する。また牛骨も家畜の数と一致する。飢饉の悲惨さは筆舌に尽くしがたい。村民はもちろん、親兄弟も凄まじき修羅と化し、その様はもはや人の営みとは呼べないものだっただろう。このことは誰にも語らず、その村の記録は破棄し、廃村として届けよ。また南村に咎を求めることもできまい。人が食い合う悲惨さは繰り返されてはならないが、このことが話されるのもはばかりあることである」